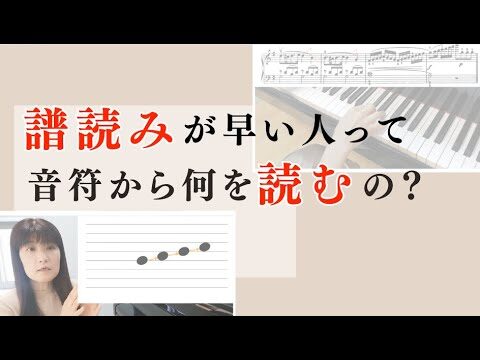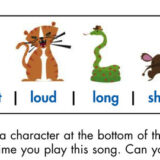日本のよくある音符指導だと
わかる音から縦に辿って読む方法
が多いですね。
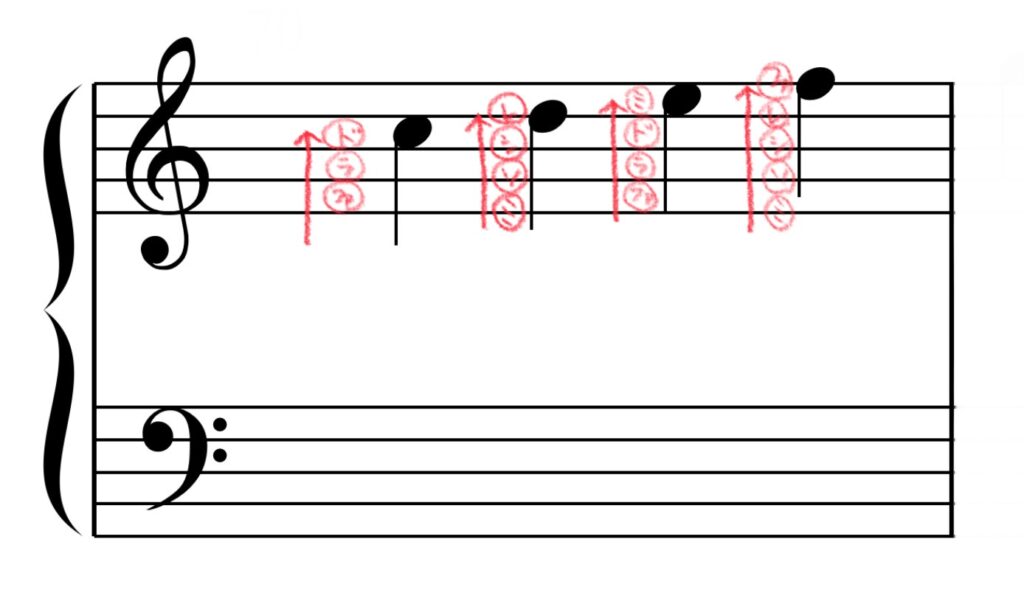
これを「1音読み」などと呼んだりします。
この「1音読み」。
たしかに音名は読めるのですが、
前後の音との関係性・流れがわかりにくい…
だからがんばって1音ずつたどって弾いても
音楽を想像しにくく
なかなか弾けるようにはならないのです。
一方、アメリカ指導など海外の場合は、
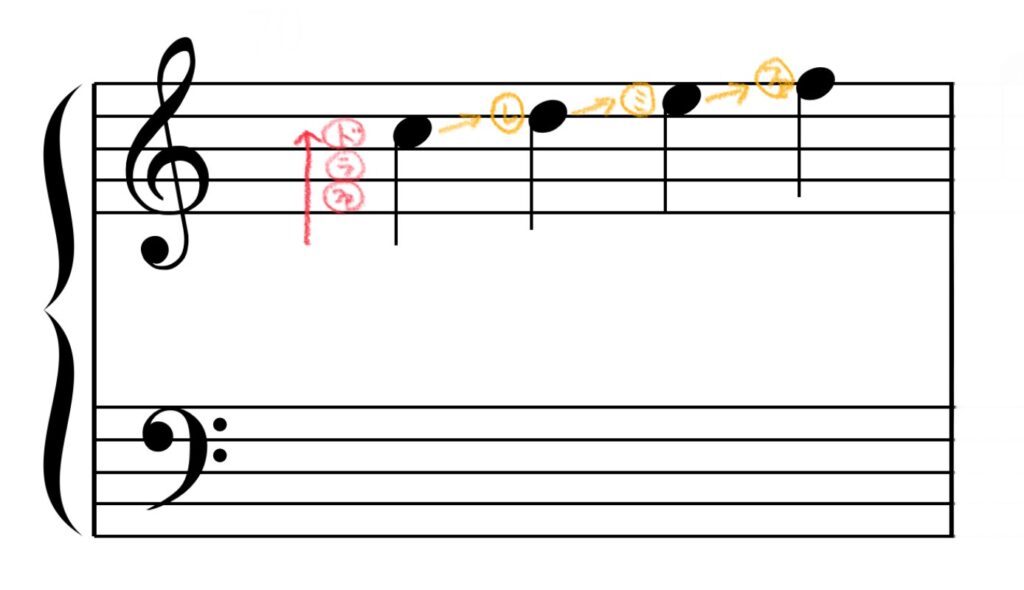
1:最初の音はわかる音から縦に読む
2:2音目以降は横に読む
の方法。
この横に読む方法を
「音程読み・模様読み・クレ読み」
などと呼びます。
この方法だと、音名がわかるだけでなく
・メロディーがわかる
・指の動きがわかる
ので
音楽が想像しやすく、
弾けるようになるのが早いのです。
そのため
ピアノアドヴェンチャーでも
ブックBや導入書などの導入時期から
横に読む「音程読み」を学んでます。
とはいえ
パッと見て「何の音か?」を
瞬間的に判断するのも大事。
もちろん日本式の「1音読み」も学びます。
例えばレベル1「紙ひこうき」では
[高いドレミファソ]の音符を学びます。
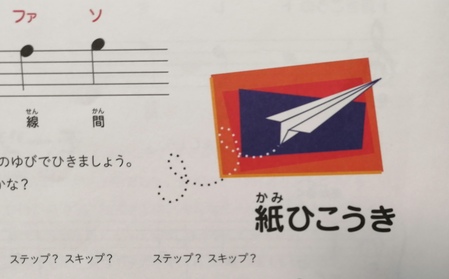
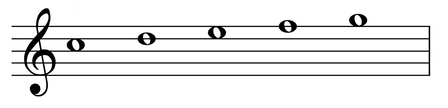
でもここで行いたいのは
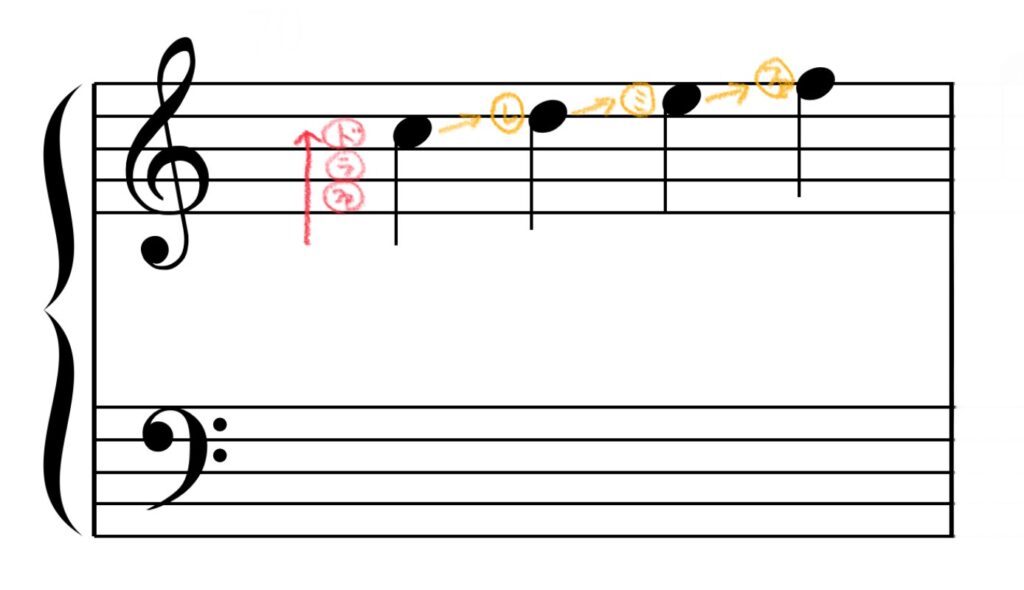
1:最初の音はわかる音から縦に読む
2:2音目以降は横に読む
の「音程読み」。
テキストにも、
[ステップ(隣の音)/スキップ(飛ばす音)]など
音程読みの理論課題があります。
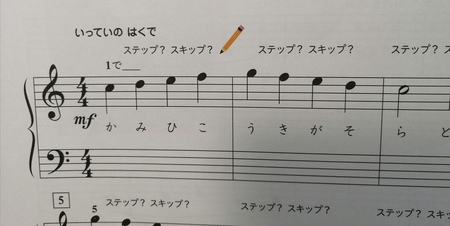
この音程読みは
今までずっとやってきたことなので
問題なく解けるのですが
意外な落とし穴があります。
それは
「音程読みで譜読みをしてない…」
というケース。
というのも

じゃ、音名で歌ってみて!
というと、

ドレ…ミ…ファ…🎵
と、なぜかつっかえる…
たしかに馴染みがない音符は
つっかえるのも分かります。
でもスムーズに歌える生徒さんも多いです。

何が違うの…?
と考えると、
今回のように「音符の読み方」が出てくると

音符を1つずつ読まなきゃ…
と思いがちのようです。
すると今まで行ってた「音程読み」よりも
「1音読み」を優先してしまって
つっかえるんですね。
本来行いたいのは
「1音読み/音程読み」の両方。
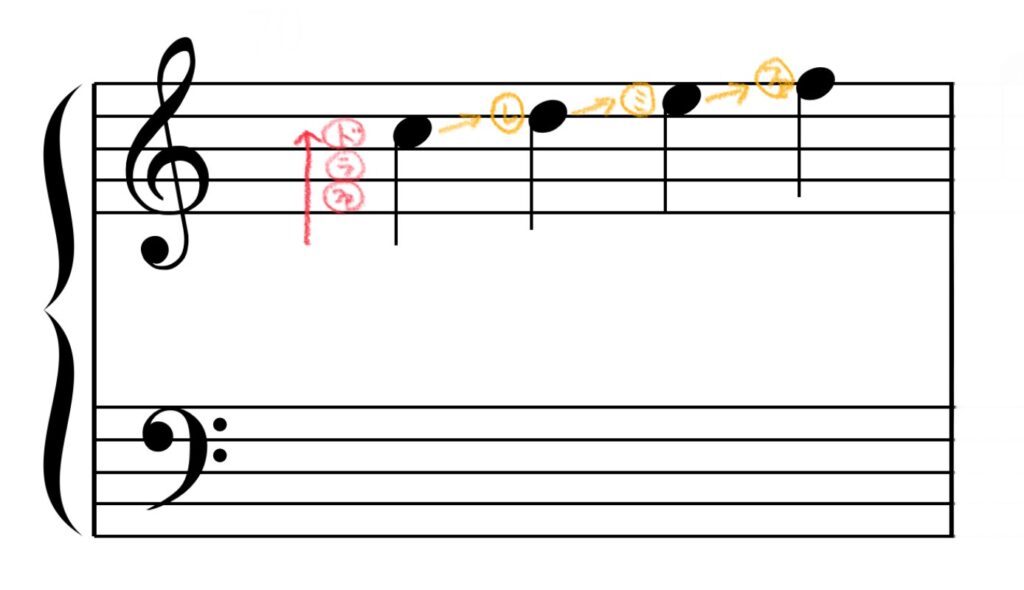
そこで
音名が読めないような課題をつかって
音程読みの練習。
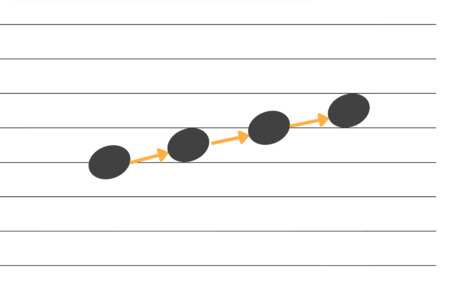

すると

音程を読むって
こういうことか!
と「音程を読む」ということを
理論で終わらせるのではなく
ちゃんと実感できるし、活用もできました。
いくら下のような理論がわかってても
ちゃんと演奏に活用しているか?
は分からないですね。
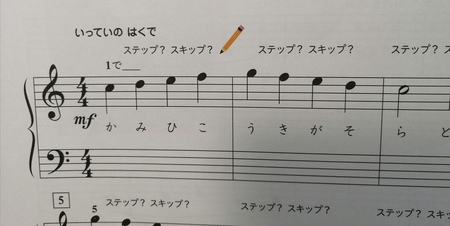
なので、
「学んだことをちゃんと活用しているか?」
を確認する必要があるのを感じた課題でした。
あ、音程読みに関する動画もあります。
ご興味があればどうぞ!
・音程読みのメリット
・音程読みの実践方法(バイエル88番で)
・音程読みをスムーズにするために先生方が工夫していること
などをお伝えしています。
 ピアノ指導の教科書
ピアノ指導の教科書