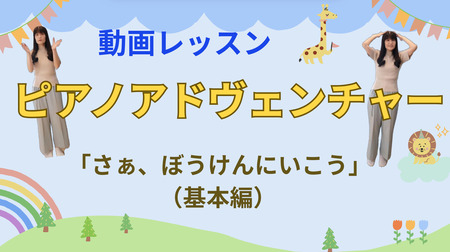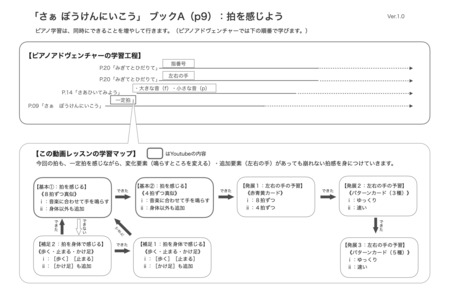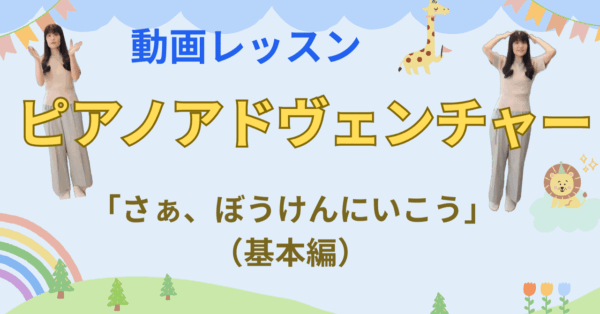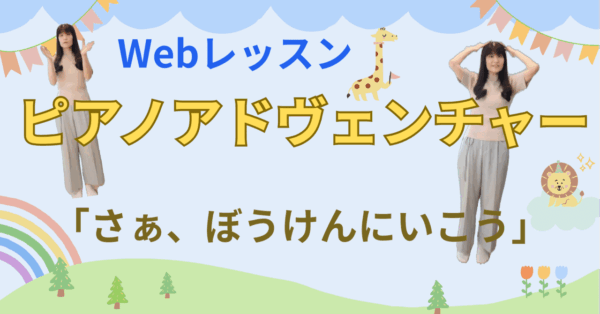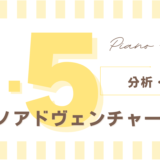はじめてのピアノアドヴェンチャーで
大人気の曲です。
思わず体も動くし、
何度も聞きたくなりますね。
そんな人気の曲は、
毎回のレッスンの定番
にするのがオススメです。
でも毎回同じでは面白くない…
生徒さんも飽きてしまいますね。
そこで生徒さんの力量に応じて
少しずつ方法を変えると
飽きずにやってくれます。
体験レッスンで使うと
とても喜んでもらえますよ。
リズムの躍動感の土台が 拍感
音楽の楽しさの一つが、
リズムに乗ること。
アイドルのコンサートなどで
ノリノリで踊ったり、

せーの!
など 、
みんなと一緒に動作をするって
「音楽ができる・できない」
関係なく楽しいですよね。
そんなリズムの土台
となるのが「拍
」。
拍を感じないことには
リズムの楽しみは得られないです。
正しいリズム の演奏の土台も 拍感
また、ユニット5では
4分音符などのリズムを学びますが、
拍が整ってない状態で
[4分音符=1拍][2分音符=2拍]
を覚えても、
ノリよく弾けなかったり…
テンポキープができなかったり…
自然な演奏が難しいですね。
なのでリズムや音符を学ぶ前に、
まずは「拍」を感じるのが重要です。
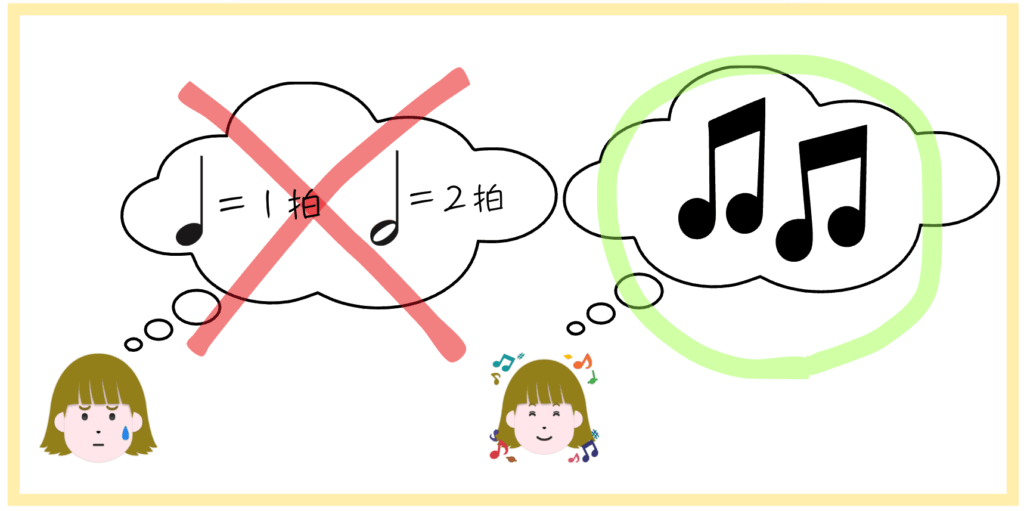
目標:リズムや強弱などの要素が加わっても 一定拍で弾ける。
ピアノを弾く時って、
・拍を感じる
・リズムを読む
・指番号を読む
・音の高さを読む
・メロディーを歌う
・ハーモニーを感じる
などとても多くのことを同時に行います。
でも複数のことを同時処理できないと
止まります。
なので、
他の要素が加わるたびに崩れない拍感を確認します。
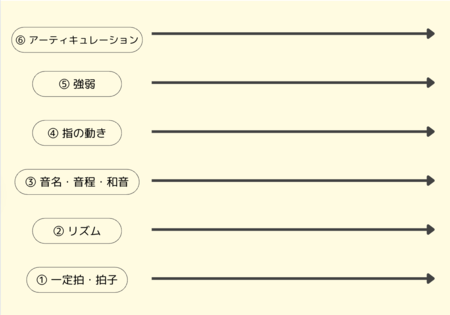
※導入編:基本編をスムーズに行うための準備
基本編:定番の使い方
発展編:学習内容の定着を深めたり、初見力を養うための指導内容
緑枠:聴く活動 青枠:理解する活動 黄枠:テクニック活動
基本編:音楽に合わせて、いろいろな場所をタップする
※基本編:定番の使い方
この段階では、拍がズレててもOK!
楽しそうにしてればOKです。
少しずつ精度を高めたり、
他の要素(指番号、2分音符)が加わっても崩れない拍感を目指しましょう。
発展1:赤青黄カードを見て、左右の手を鳴らす
※発展編:学習内容の定着を深めたり、初見力を養うための指導内容
ピアノアドヴェンチャーの場合、
次に学ぶ内容はこうなってます。
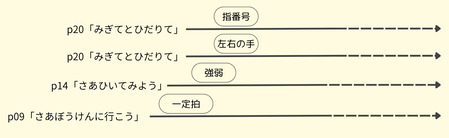
ごらんの通り、
あと10ページもすると[左右の手][指番号]
が出てきます。
なので、
「この曲楽しい!」と思ってる間に
[左右の手]の予習をおすすめしてます。
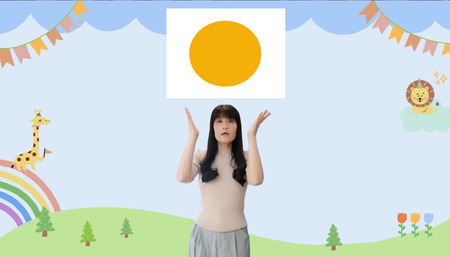
発展2:4音カード(3種)を見て、左右の手を鳴らす
アメリカ指導は音符をグループ化して読む「パターン読み」が定番です。
そのパターン読みの入口として、
左右の手もパターン化します。
もちろん「拍のキープ」も行いながら。
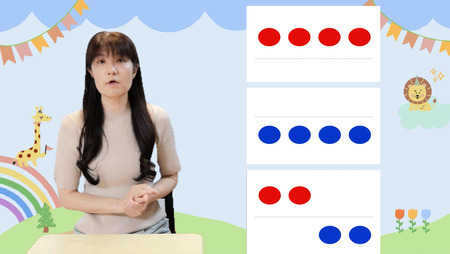
発展3:4音カード(5種)を見て、左右の手を鳴らす
続いてパターン読みです。
今度は2種類を追加し
合計5種類を見分けながら鳴らします。
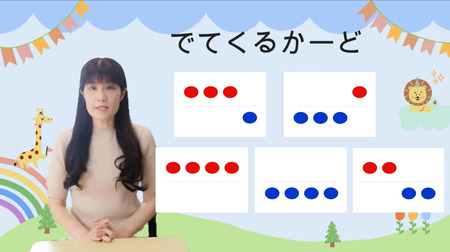
発展編の動画・指導案・カードがセット。
次の補足編の動画・指導案も含みます。
補足1・2:身体を使って拍を感じる
とはいえ、
・そもそも拍を感じてない…
・合わせる気がない…
という場合があります。
そんな時はリトミックがおすすめ。
内容は同じですが、
2種類の音楽をご用意しました。

補足編の動画・指導案がセット。
前の発展編の動画・指導案・教材カードも含みます。
リズムに乗るって楽しい!
この段階では、できてなくてもOK!
まずは「リズムに乗るって楽しい!」
と思ってもらうのが大事です。
とはいえ、
・精度の高い拍感
・他の要素が加わっても崩れない拍感
を養うのも必要。
なので他の概念(2分音符、指番号など)を加えたりして、
少しずつ課題内容を発展させながら、
時には曲を変えながら
毎回のレッスンで継続します。
くわしい内容はこちら
 ピアノ指導の教科書
ピアノ指導の教科書