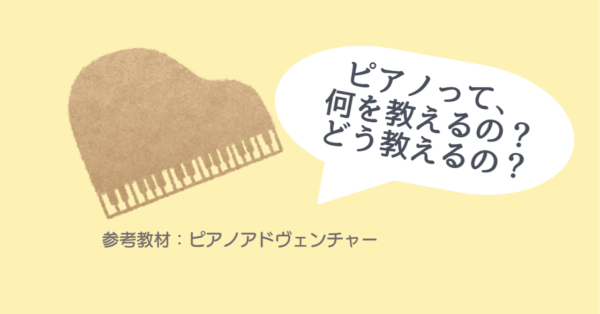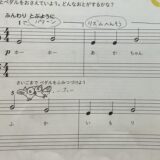大人生徒さん。
左手Ⅴ7[シファソ] が
[ドファソ]になる・・・
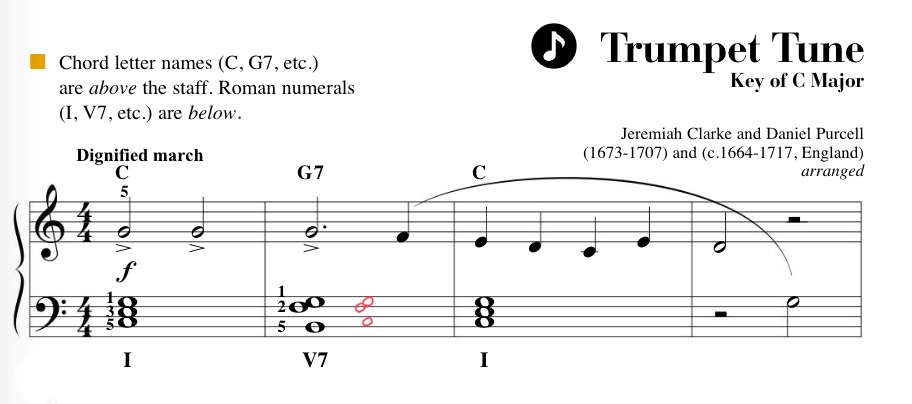
しかも間違えたことに気づいてない…
昔の私だったら
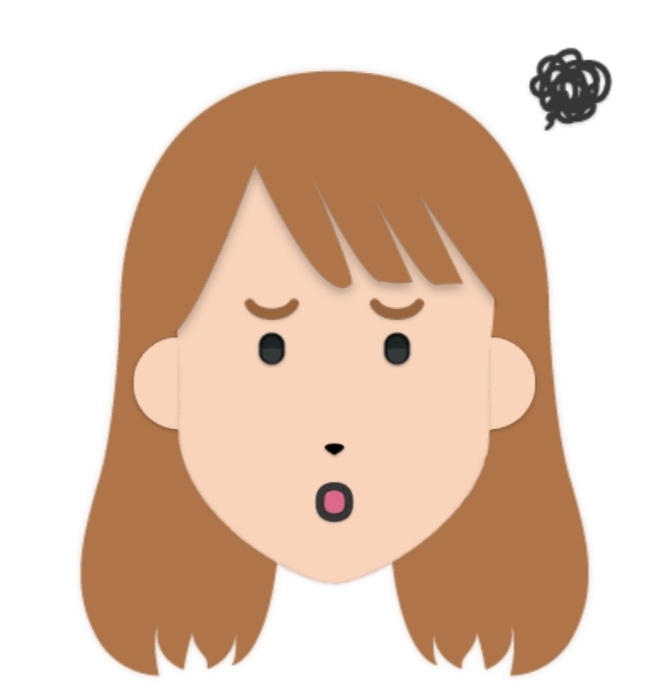
[ド]じゃなくて、[シ]ですよ!
と、音の間違いを指摘するだけ。
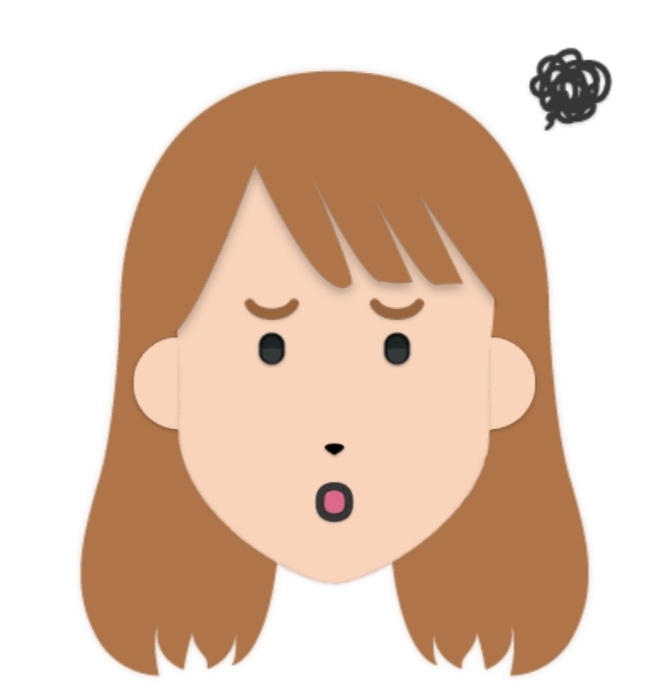
気をつけて!
できるまで練習して!
と量を求めるだけだった。
もちろんこれで弾けるようにはなる。
何十回と練習すれば。
でもそれは対処療法であって
根本的な解決にはなってない。
また同じような間違いになる。
なので、根本的解決をレッスンで行う。
原因は何?
原因は色々考えられる。
《譜読み工程》で考えると、
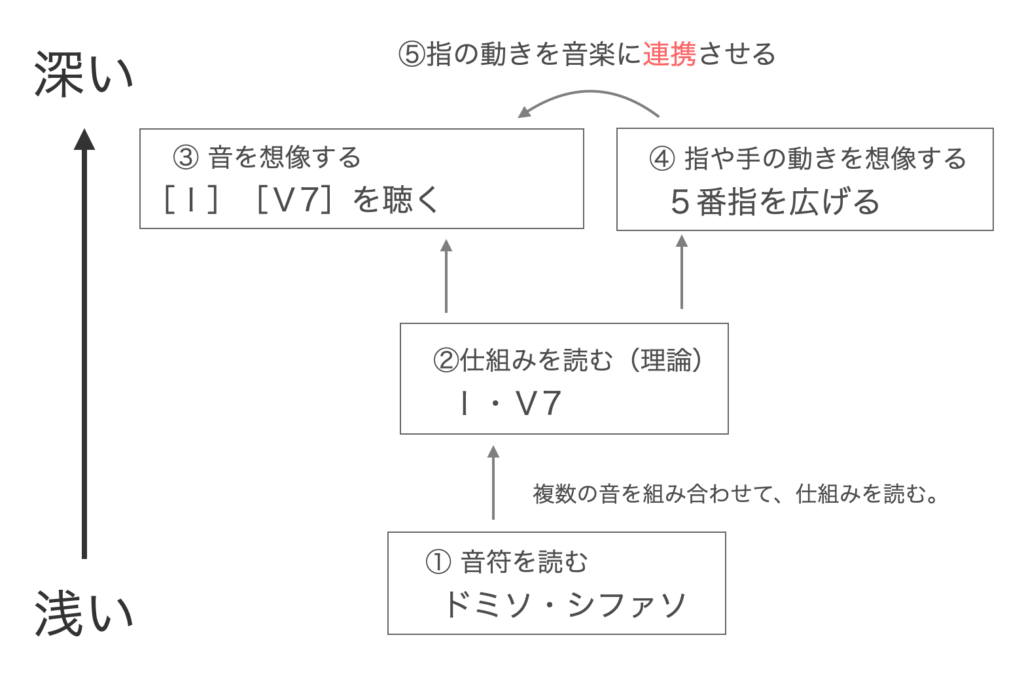
①[ドミソ][シファソ]の音符を読めてない。
② [ドミソ= Ⅰ ][ シファソ=Ⅴ7]の理論がわかってない
③ Ⅰ・Ⅴ7の響きを想像できてない。
④左手5番の指を広げる感覚ができない
⑤音を想像しながら弾くができない。
のどれか。
今回の生徒さんの場合、
・今までの様子
・「間違えたことに気づいてない…」
からすると、
おそらく「聴いてない」が原因。
《譜読み工程》の
③の音を想像できてないが原因。
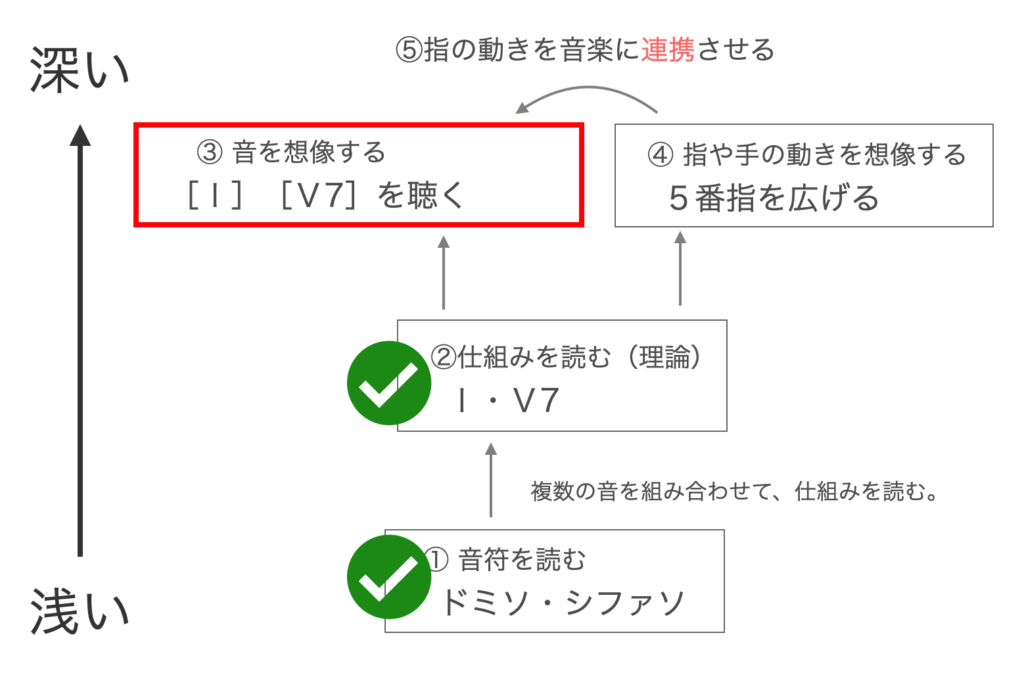
なので
③の音を想像するの改善を行う。
どう指導するの?
でもその
「③音を想像してるか?の確認」
って案外難しい。
なので今回は
聴き分けができるか?を行う。
聴き分ける音は
・ Ⅰ[ドミソ]
・Ⅴ7[シファソ]
・間違えてた[ドファソ]
の3種類。
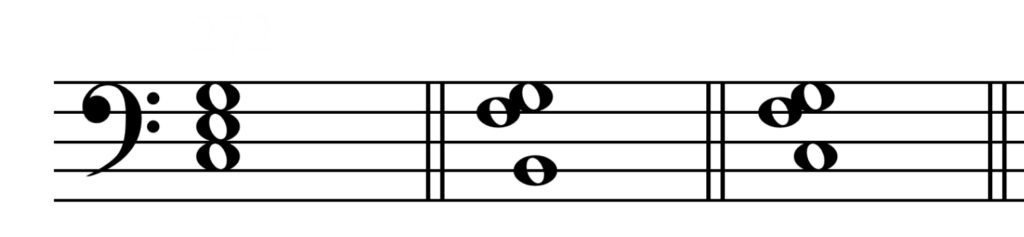
その聴き分けを行うことによって
そもそも「聴く」も行いたい。
生徒さん。
これは難なくできました。
となると図の③はOK。
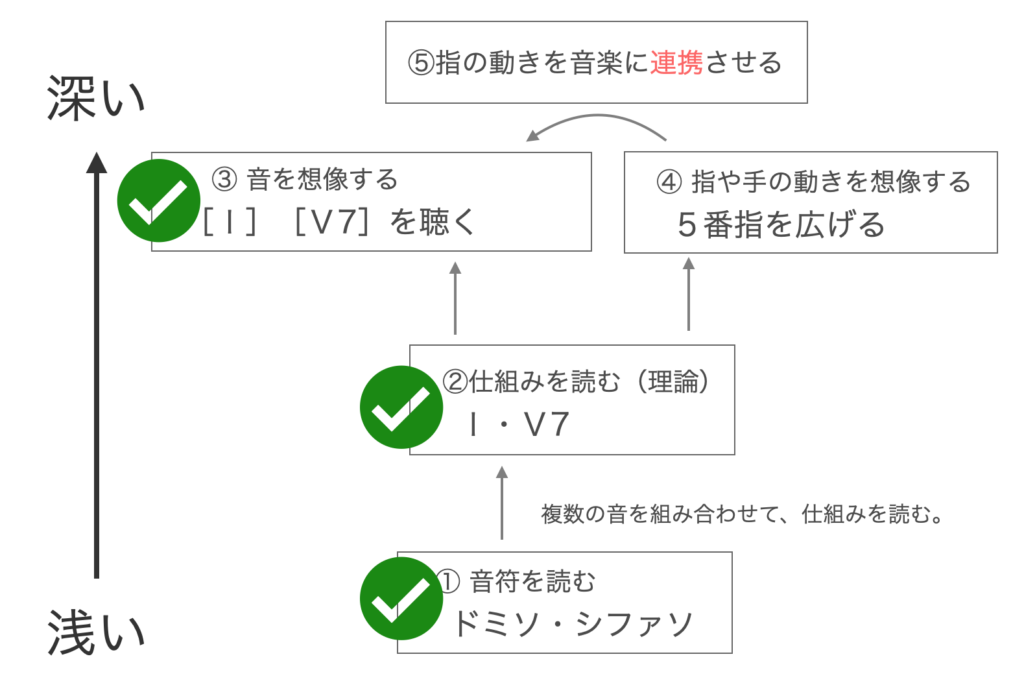
ということは、
基本3要素(理論・聴く・テクニック)
はあるけど、
・聴き方が分からない
・聴く余裕がない
が原因かな…?
となると
⑤の連携に問題がありそう。
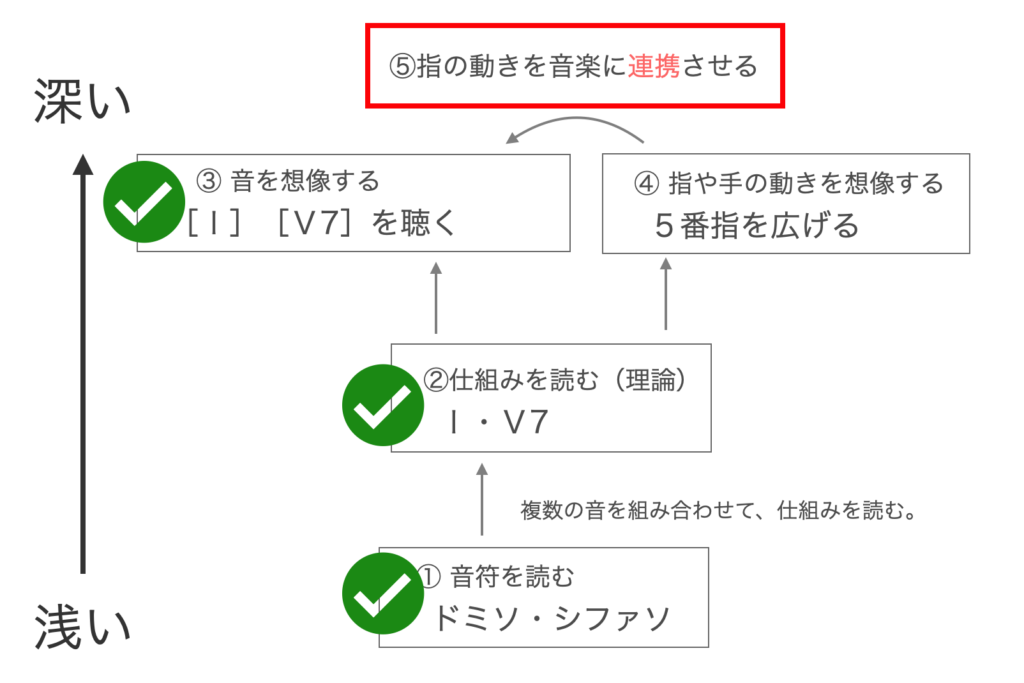
というわけで今度は
その[ Ⅰ ][ Ⅴ7]を聴きながら弾けるか?
と⑤の確認。
もしできなかったら
④の5番の指の動きを確認する。
弾いてもらったら
音に引き寄せられるように
自然に指が動いてる。
さっきの
③音を想像する練習が効いてる。
なので大丈夫そう。
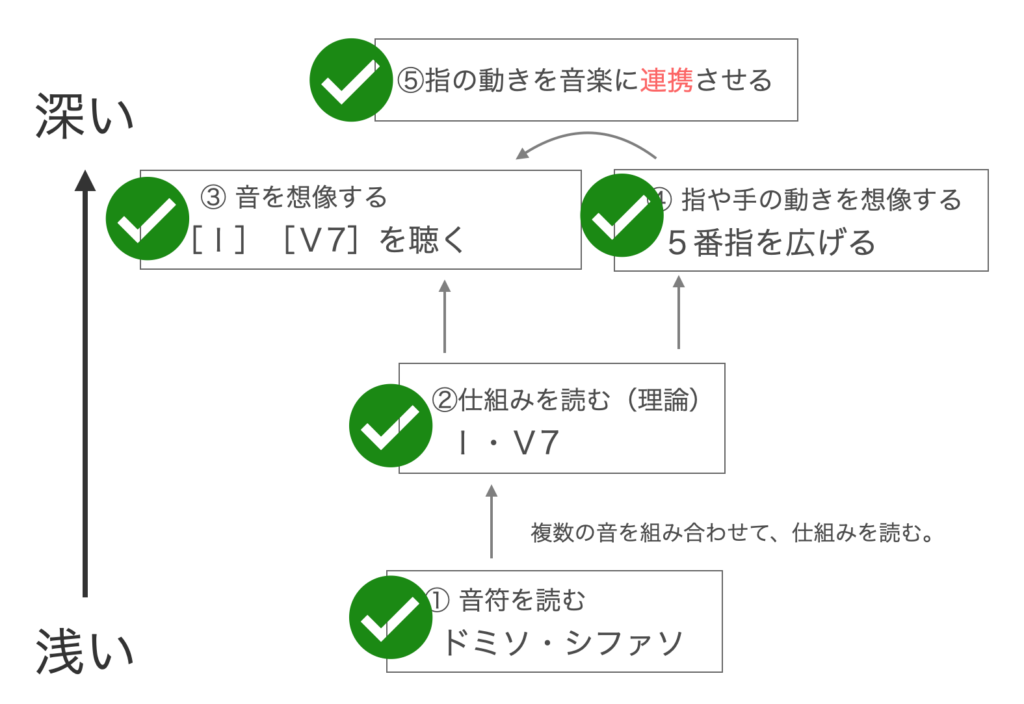
これで一応弾けたことになる。
どう指導するの?(応用編)
でも、これを応用しても弾けるか?
を行う。
というのも
概念(音楽ルール)を習得する工程はこんな感じ。
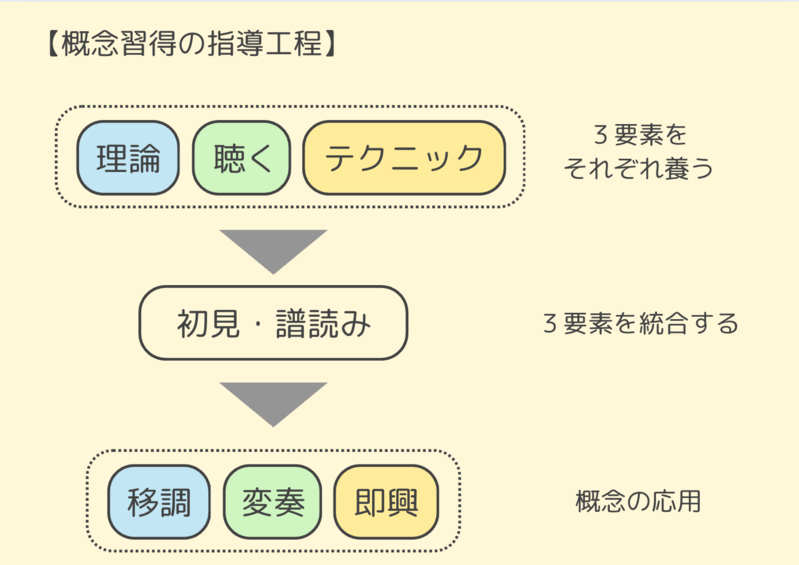
①3要素(理論・聴く・テクニック)の確認
②初見や譜読みで3要素の統合
③概念の応用
今回身につけたい概念は
[ Ⅰ ][Ⅴ7]。
近い将来、
これを使いこなせるようになって、
[ Ⅰ ][Ⅴ7]を含む簡単な曲程度は、
初見で弾けるレベルに持っていきたい。
んで今、
【指導工程②:統合】まではできた。
算数で言うと、
計算問題はできる状態。
次は文章問題が解けるか?
の応用段階に入る。
ピアノ指導で言うと、
移調:理論がわかってるか?
音程・和音が聴けてるか?
変奏:他の概念が加わってもできるか?
即興:楽譜がなくても統合ができるか?
を行う。
んで今回は移調。
理由は、
「音程を感じてるか?」
を確認したいから。
なので
Gメジャーに移調して弾いてもらう。
生徒さん。
移調自体は慣れてるし
Gメジャーの場所もすぐに探せた。
移調もOKだった。
これで
譜読みはできてることがわかる。
とはいえ今回の根本的原因は
「聴いてない」。
一応今回の曲は大丈夫だけど
まだ「聴いてなかった」→「聴きながら弾く」
を行えたばかり。
概念習得も
まだ変奏や即興を行ってないので
身についた!とは言えない。
なのでしばらく様子を見て
変奏や即興を行おうと思う。
 ピアノ指導の教科書
ピアノ指導の教科書